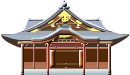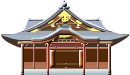
造胎異誌
(「古道」より)
昭和二十一年八月一日
清水瓢伯 訳
漢談生という者があった。
年が四十に垂んとしていたが、まだ獨身でいた。
生計(くらしむき)のことなど一向に無頓着で、常に詩経を読んでは感激していた。
仲秋の夜、談生は明月を仰いで、獨り詩経を朗読していた。
心が澄みきって、嵩然(こうぜん)として、遥かに俗世を捨てた思いである。
詩興の赴くままに談生は感激して、ぽろぽろと涙を流しながら、朗誦を続けていた。
いつの間にか夜半に及んだ。
庭前にひそかな人の気配がしたので、朗読を止めて窺ってみた。
それは十六、七歳の少女で、その容色の美麗なること、天女かと見まがうほどであった。
夜目にもしるく、錦繍の美服を纏(まと)っていた。
談生を見て、嬉しそうに笑って話しかけた。
少女もまた詩経が好きで、日頃これを愛誦しているとのことであった。
二人はたちまち意気投合して、懇(ねんごろ)になった。
原著には、「遂に夫婦の言を為す」とある。
少女は談生に固く約束して云った。
「私は普通の人間ではありません。
しかし、決して物の化(け)のような怪しいものではありません。
三年経(た)てば、すべてが判ります。
それまでは、決して燈火(ともしび)で私を照らさないで下さい。
これだけは固く固く約束して下さい。」
談生は不思議なことに思ったが、承知した。
間もなく少女は懐妊して、一子を生んだ。
玉のような男の子であった。
その子が二歳になった時のことである。
或る夜、談生は好奇心に駆られて、固い約束に背いて、少女が寝入ってから、そっと
燈火で照らしてみた。
榻(ねだい)に横わって、スヤスヤと寝入っている少女は、色は透きとおるほど白く、
肉づきも豊満で、うっとりするほど美しいが、両脚は、只二本の骨組みだけで、全く
肉がついていないのである。
談生は思わず、あっと駭(おどろ)きの声をあげた。
少女は目を醒まして、きっとなって云った。
「とうとう貴方は約束に背いてしまったのですね。
あと一年が、なぜ待てなかったのですか。
すべては水泡に帰してしまいました。
もう、何もかもお仕舞いです。
お別れせねばなりません。」
談生は泣いて謝ったが、少女は肯かなかった。
「あなたの詩魂に感じて再生を希(ねが)って來ましたが、もうこれまでの縁です。
永久にお別れせねばなりませんが、この子供がかわいそうだと思います。
あなたは詩経ばかり読んでいて、とても子供を養うことなど出来ないでしょう。
私が生計(くらしむき)の道をつけますから、一緒に随(つ)いていらっしゃい。」
談生は少女に随(つ)いて外に出た。
仲秋の明月が、二年前、はじめて少女と相逢ったときのように、中天に照りかがやいていた。
談生は、とりかえしのつかぬ心持ちで、自らを哀みながら、とぼとぼ歩いた。
ふいに、立派な殿閣の前に來た。
こんなところに、いつの間に、こんな立派な玉樓が出来たんだろうと、談生は不思議に思った。
家内の装飾、調度品も目を奪うばかり華麗で、とても凡人の住居(すまい)とは思われなかった。
少女は、一枚の繍入りの美服を取り出して、談生に与えて云った。
「これを市(まち)へ持って出て、目隹(き)陽王の家へ売りなさい。
きっと自活(くらし)の道がつきますから。」
そして、談生の片袖をぴりぴりと裂きとって、
「これは形見に戴いていきましょう」
と云った。
翌々日、談生はその刺繍入りの着物を持って市(まち)に出て、目隹(き)陽王の家へ売った。
王の家では数百金を價として呉れたが、帰途談生は、忽(たちまち)警吏(やくにん)のために呼び返された。
目隹(き)陽王は、この刺繍入りの珠袍に、見覚えがあったからである。
この着物は、三年前に死んだ王の一女(ひとりむすめ)のもので、死体と一緒に棺の中に納めた筈である。
どうしてこの着物が談生の手に渡ったかと訊(き)くのである。
王は、きっと談生が冢(はか)を發(あば)いて盗み出したに違いないと考えたのであろう。
談生はありのままをを答えたが、王はそれを容易に信じようとはしなかった。
遂に人を遣(や)って冢(はか)を調べさせた。
冢(はか)は故(もと)の通りで、何の異常もなかった。
王は愈(いよい)よ不思議に思って、遂に冢(はか)を発掘して、棺を改めさせた。
少女が形見のためにと云って、談生から裂きとった片袖は、棺の蓋(ふた)の下に留っていた。
子供が呼び寄せられた。
その子は死んだ一女(ひとりむすめ)に生き写しであったので、王はもうただポロポロと涙を落として、
感慨無量といった態であった。
談生は王の女婿として面倒を見て貰うことになったので、少女が言ったとおり、生計(くらしむき)には
困らなかった。
子供は再び談生の許(もと)に帰されたが、非常に怜悧(りかつ)であったので、王もいとおしきことに思い、
よく呼び寄せては可愛いがった。
後にこの子は、郎中の職にまで出世した。
訳者曰く、これは捜神記中の一篇で、この原文は宮地水位先生の「仙人下尸解法訣」の中にも引用されて
いる。
水位先生は、「思うに是は、死したる時に、尸解の法にて屍を取り出したるが、其後、屍を調製する法に
よりて、肉体を作りて人に嫁したれども、神仙の掟に屍を調製し竟るは、死して三周とて、三年、其の死したる
日に廻り逢うまでは、具足して人間に出づるを禁じたるものなるを、其の調化の期來ざる内に形を造りたるを
以て、未だ作り得ざる形を現じて、腰より以下に枯骨を現したるものなり。
又、形を造り竟らぬ間には、燭火を大いに忌むものにして、燭火を一つ燭して見るは、基本体を見る神仙の
秘法なり」と註して居られる。
斯うした例とは、別に幽鬼(あのよのもの)が人間と情を通じたというような話は枚挙に遑(いとま)ないが、
これは胎の本質を異にするので、子を成すまでに至らない。
尸解法によりて再び肉体を調製し、人間に婚嫁して子まで産んだという此種の実例は、珍しいことである。
また卑俗な方面で、狐妻を得て数年、或は数十年間同棲した挙句、子まで成したというような伝説は
数限りなくあるが、支那のそれは、日本のそれに比して、極めて現実的である様である。
南柯の一夢といった頼りなさや、怪談めいた凄みはなくて、人間界との接触が極めてスムースに、生活面に
親しみ深くタッチしているようである。
聊斎志異あたりを一読しても、此の間の消息を窺知するに難くない。
これは、彼の地の次元交渉の特異性――霊界の地方色(ローカルカラー)とでもいうべきで、一面民族、
伝統、信仰、土俗といった一連の背景の交流して、「支那」という、おおらかで多彩な神秘なすがたが、
謎をとくように窺えて興味津々たるものを覚える。
|