   「古道」より 「古道」より  
清水斎徳
【冷厳なる反省】
昭和二十年九月一日号
大東亜戦争終結に関する大詔は換発せられた。
天皇陛下は、国民に武器を措くことを命じ給うたのである。
武力戦は、茲(ここ)に冷厳なる眼前の事実が示す通り、最悪の状態を以て局を結んだのである。
悠久三千年の歴史を通じ、曾(かつ)て誰一人として味はなかった異常なる感慨を、吾らはいま、
現実感として噛みしめているのである。
△事茲(ここ)に至った原由に就いては、遠由近因多くのものが挙げられるであろう。
然し、其の最尤最大なるものが、国民道義の頽廃にあったことは、当局の指摘するが如く否めない事実である。
それは、誰れ彼れなにがしだけの責任ではない。
一国の運命を賭した曠古の大戦に際して、国民は果して滅私奉公、破れて悔なき戦いを敢行したであろうか。
それは国民の一人々々が自らを眩ませずに厳粛に反省すれば判ることである。
他を責める前に、自らを懺悔すべし。
神を疑う前に、自らを疑うべし、
神を嘲る前に、先ず自らの良心の責任を痛感すべし。
日本民族の血類にして、神を嘲る資格を有するものは、誰一人としてあり得ないのだ。
況(いわん)や、玄妙の神意をや、萬古の神籌をや。
△今、議会に賜りたる勅語において特に、「道義立国の皇謨」を御宣示あらせられ、また首相宮殿下は、
「われわれはいまこそ、総懺悔し、神前に一切の邪心を洗い清め、過去をもって将来の戒めとし、
心を新たにして、戦いの日にも増して挙国一家乏しきに分ち、苦しみをいたわり、温かき心に相授け相携えて
各その本分に最善を竭し、来るべき苦難の道を越えて、帝国将来の進運を開くべきである」と昭かに
御示しになっている。
茲(ここ)において曩(さき)に政府が宣明する、「国体護持」の観念も、極めて冷静に慎重に深思されねばならぬ
のである。
吾々の神祇信仰の根幹が、信念の基盤が全く不動のものであることは、已に昭々として明かである。
内在する信念こそは、過去と現在と将来を貫く、天衣無縫の存在なのだ。
而(しか)して、吾らの信仰の対象が、将来に向ってより的確に、より強固に開展せらるべきことは、固より
論を俟(ま)たないところである。
△吾々は「旅」の過程に、余りにも概念的な担途の夢を追ってはいなかったであろうか。
荊棘に繋る道に非ずと断定し得ると思っているであろうか。
△吾らは大御心に副い奉る為、内には愈(いよい)よ正眞の魂魄を澡雪錬磨し、徹上徹下艱難のミソギを
受け尽くし祓い尽くし、人の道を尽くして神の前に立たねばならぬのである。
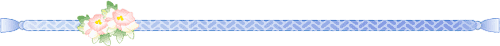
【一言双語】
昭和二十年十月一日号
一寸古い話であるが、中村不折書くところの観音大士に、伊藤博文公が讃をしたのを見て、不折氏が激怒した
とかいう話しがある。
◇伊藤公の勇気には、毎々敬服の外ないが、これは不折氏の怒るのがあたり前であると思う。
伊藤公の所謂る審美眼や、筆力の深浅を云々しているのではない。
勿論、大勲位公爵という、伊藤公の肩書きに不足があるわけでもないが、相手が観音さまと来ているので、
一寸始末が悪いのである。
◇不折氏も、何も時分の書いた繪に讃をしたことを怒っているのでは、恐らくあるまい。
問題は、観音大士に讃をしたことにあるのである。
その境界を得ざるものが、濫(みだ)りに「境界」の押し売りをして、恬としている陋劣さに、芸術家としての潔癖が
爆発したのであろう。
◇いくら国家の元勲という伊藤公の権勢を以てしても、この無位無爵の観音大士の一毫髪にも歯のたつところは
ないのである。
否な、筆者の不折氏自身にしたところで、一たび筆を投じて大士の霊機に参ずるや、更らに一点一劃の加う
べきを許さぬ大霊威の示現に、ただ帰命頂礼あるのみである。
そこが宇宙の権威であり、世の中の恐ろしいところである。
◇人あり、伊藤公には此の観音大士の讃を乞うたとして、公がただ黙って之を拝して辞したとしたらどうであろう。
それは伊藤公のために、決して恥でもなければ、怙券を損ずる所以でもない。
不折氏がそれを聞いたら、不折氏は又た黙って、伊藤公を拝むであろう。
伊藤公の心の裡に、うるわしい観音大士の霊姿が、ありありと示現しているからである。
すでに、観音大士と同坐しているからである。
◇ただ黙って、観音大士と同坐するだけでもよいが、更らにこれを家来にして駆使する心とは、少しも矛盾する
ものではない。
その境界は、判るものに判るだけのことである。
◇吾徒の書く観音さまは、散て紙筆を用いず、以て丹青を塗抹することを要せず、随意髄所に時計の音の中から
でも松籟の響きの裡からでも、また淙々たる渓流の音の中でも、思うがままに、之を書くことが出来る。
その天衣無縫、千変自在の筆致は、鬼神と雖(いえど)も、筆を投げて讃を辞するであろう。
この没縦跡の名画こそ、さらに凝思の痕跡をとどめぬ無適の妙境で、只だ洞然として本源の眞気に見参するのみ
である。
惚たり恍たり、其の中に象あり、窈たり冥たり、其の中に精ありである。
この「自画自賛」の妙境こそ、吾徒が天上天下の生類にその福音をのべ布かんとする観音三昧の妙相、「おとだま
観音」の功徳である。
◇坐り続けて二十年、音霊とともに二十年、汲めども尽きぬ音霊の深い、明るい、うるわしい霊気に包まれて、私は
限りない人生のよろこびを味わいつつ過ごして来たのである。
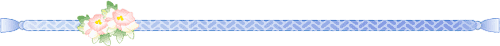
【丹田鎮魂の説】
昭和二十年十一月一日号
気海丹田の説は、古来いい古されたもので、陳腐といえば極めて陳腐な説である。
もと道家から出たものであるが、用語こそ異なれ、仏家でも儒家でもいうし、又た静坐法や呼吸法や保健法、其他
霊術の徒までが、柄(がら)相応に擔(かつ)ぎ回る代物で、霊学に志すほどの者で、此の説の洗礼を受けない者は
恐らくあるまいとさえ思われるが、それでいて、云うほどに手に入っていないのも亦(また)、この説ほど身について
いないものはあるまいではないかと思うのである。
老子が、吾が言
甚(はなは)だ知り易く、甚だ行い易し。
天下能く知る莫し、能く行う莫しと言った消息を、仮りにこの説に応用してみると、興味のある観察が下される。
道家では、臍輪のところを気海と称し、臍下一寸五分のあたりを丹田と呼ぶが、気海とは要するに、周身の元気の
集中する海というような意味、丹田とは丹(道家で不老不死の仙薬を丹と称する)を産出すべき田地という意味から
名づけたものであろう。
丹田の位置については、臍下一寸五分といい、また二寸とも二寸四分とも、三寸とも伝えられ、諸説一致を
見ないが、これは解剖学的に究明せらるるべき性質のものではなくて、臍輪気海丹田と複合名詞にして、総称
されている場合もあって、要するに臍からかけて、臍下二、三寸一圓を称するものとしておく。
(丹田には元来、上、中、下の三丹田があり、神仙道の伝承として、別に深遠な消息もあるが、茲(ここ)では煩を
避けて、下丹田のみを丹田と通称しておく。)
ついでに、臍に関する無駄話を一つ、「軽口浄瑠璃」に、凡(おおよ)そ五体のまん中に、位いはすれども何一つ、
役に立ちたる例(ためし)なし。
厄介者よ、能なしと、疎んぜらるるが口惜しさに…などとあるが、果してそれ程、能なし的存在であろうか。
無駄話の序(ついで)に、若干臍の経歴について触れてみよう。
臍は元来、臍帯のとれた痕跡で、此処に繋がっていた臍帯は、二條の縄筋で、其の一端は胎盤によって母体に
連り、一條は母体より血液の輸送をうけて自己の体を養い、他の一條は、胎児の新陳代謝の結果生じたる
不要物を、母体の血液に排出還元する通路となって居り、胎児はこの臍帯によって生活を営むのであるが、
単に母体よりの輸血ルートたるに止まらず、胎児が結胎成長するに必要な、天地生々の諸気をも伝導される
ところで、すなわち臍こそは、吾々が出生前からして天地の眞気を享(う)けはじめた、人身元気の接触交流点で
あり、心身力点の中心であり、其の前身は明(あきら)かに、身体の中府とも称すべき存在であったのである。
臍を力点として、胸部及び腹部の交感神経は、已(すで)に胎児のうちに、十分形成されてしまうのであるが、
その頃、脳は所謂(いわゆ)るクラゲナス、タダヨヘルモノで、ドロドロの塊りに過ぎないのである。
交感神経、すなわち自律神経が早くから出来るのは、頗(すこぶ)る意味のあるもので、早くからその働きを必要と
するからで、全身に栄養を送り、排泄作用を全うし、五臓六腑を完成し、その機能を支配し、骨格をつくりあげてゆく
ことは、脳脊髄がなくて一向差支えはない。
脳髄が主として外界と交通する機関であるに対し、直接生命を保持し、生命力の消長を左右する自律神経は、
内的な世界に交渉する機関であるといえる。
ミウルレル氏によって、「生活神経(レーベンスネルフェン)」と命名されている、此の交感神経の神秘なる作用は、
臍を力点として、深き内観の世界より、発現したものである。
胎児が分娩と共に臍帯を裁断されるや、臍はその瞬間から、もはや単なる前世紀の遺物として、天然記念物的な
存在に陥ってしまうのであろうか。
人身の先天的機関であり、元気湊曾の根本府たりし人間の臍は、単に木から落ちた果実の蔕(へた)如き存在では
ない。
道家で、人間の生命力の根源を、臍を中心として説いて行こうとする態度は、科学を超越した科学的態度であると
思う。
それが今日の解剖学から見て、何らの興味をも索かないものであるとしても、それは索かないものの妄であって、
人間は今日の解剖学に教えられて、はじめて生活機能を発現したものではない。
それは、天文学発生以前から、天体が存在するようなものである。
「臍輪以下、丹田の地は、人身の正中にて、肢体を運用する所の樞紐なり。
上は、鼻と相応じて天地間の鼻よりして吐調し、その外気を此の丹田より周身へ普達せしめて、内外一貫になりて、
生命を保つところの根本なればなり。
故に、婦人の懐孕(かいたい)するも、又、その種子をここに生育す。
又た胎児の子宮中に住むや、その鼻、自ら臍を覗(のぞ)くように、体を弓形にして、鼻と臍とを相対し、被膜裏より
自ら外気を感得す」
これは、幕末の名医で、桜寧主人と号した、平野元良翁が医家としての立場から述べられた所論の一節であるが、
臍輪気海丹田と生命力の関係を、簡明に論じたものといえよう。
道家で臍下丹田を錬丹の田地とするも、先天の一気を此の気海丹田に納めて、体外なる先天の一気と感通冲和
することを要義としているのである。
先天の一気とは、天地未だ剖判せざりし以前より存する元気である。
いま我らの呼吸する空中の大気は、日気、地気、火気、水気をはじめ、其他もろもろの気の混合せるものであって、
素より天地生成以後の後天の気であるが、この後天の気中にも亦(また)、自ら
先天の元気を包含するものである。
生命力の根源たる此の先天の元気を、臍下気海丹田に採納して、いわゆる我が天を以て、「事(つか)うるところの
天」に含し、無窮の生命を長養することを眼目としている。
かくして修錬の効を積みて、我が生命の本体たる眞気の霊物を丹田に保養凝結することを道家では、守一の法とも
称しているが、此の間の消息を抱朴子は、「一を知れば万事畢(おわ)るものなり」と云っている。
尤も、この語は、まだまだ幽玄な解釈と、普遍的な意義を有つものであるが、斯うした丹田修錬の工夫を、用語を
換へていえば、丹田鎮魂というような表現を用いた方が判り易いのではないかと思われる。
鎮魂とは読んで字の如く、要するに、心を鎮めることである。
令義解に鎮魂の義を解いて、離遊の運魂を招きて、身体の中府に鎮むるの儀なりとあり、火風の徳を有つ心魂は
どうしても散り易く動き易い、離遊の運魂、すなわち散逸せんとする精神を静かに下腹部丹田に収め鎮めて、冷著
冷静なる心性を修養工夫することである。
道は須臾も離る可らずというが、日常坐臥行往の間と雖(いえど)も、それと気づいた時、臍下丹田に心気を鎮め、
散逸せんとする精神を結びとどめて、心身の正しい力点を此処に求むべく、内観省察することが肝要で、
軈(やが)てそれが身につくようになって来ると、先づ精力の最善活用といった境地が打開され、内外萬縁に触れて
自得される境界は機に臨み変に応じ、悉(ことごと)くその節に中(あた)り、その和に處して、誤らざるに至るのである。
刹那の間に悠久の時を読み、一指を起して天地を包容する内観の世界は、姑く之を措(お)き、単に精力の善用と
いった方面からのみ見ても、生涯を通じて受用無尽である。
「方今の人、ただ富貴栄華を慕い、名声功利を競遂いて、飽き足ることを知らざるが故に、其の心志を外にのみ
馳せて、内に守るものなく、その外物を摂取する所の耳、目、口、鼻、の穴の方へ、一身の血気と共に、胸腹諸臓を
上へ上へと勾引し、もし腔内筋膜の繋着が無くば、臓腑は悉(ことごと)く顔面裡に引込みもしつべき状なれば、
身体は徒らに、所謂(いわゆる)将棋倒しとやらんになり、臍下空洞(がらんどう)にて、物無きが如く、下元の力
虚乏して、腰脚に力なく、腹胃漸々に狭溢なり。
日々の飲食停滞腐敗して、血液の運輸、怠慢となるなり。」
「今、之を衆人に試むるに、小腹臍下充実し、大腹に支結(むすばれ)つかえなき者は、無病なるのみならず、
精神よく安定して仁義の道を志し、決断必ずよきものなり。
又、胸脇(むね)つかえ、心下中院(みぞおち)の辺り壅塞(ふさが)り、臍下に力なきものは、必ず宿疾ありて、且つ
治し難く、其の思慮定らず。
愚痴蒙昧にして、毎事(すべて)曖昧模糊(あいまいもこ)、動(やや)もしれば、耳目の欲に惑い易く、飲食も又
停滞がちにて、多くは天寿を全うすること能(あた)わず。
たとえ偶々寿を得たるも、老耄(ろうもう)にして事用(ことのやく)に立ち難き藻の多し。」
矢張り、平野元良翁の説であるが、流石(さすが)に医家だけに、心身調和の微妙を穿(うが)ってよく説いてあると
思う。
俗に、「胸に手を置いて考えてみよ」と云うが、胸だけではいかぬ。
茲(ここ)に引用した前二項を繰返し体読して、瞑目沈心、胸に手を置き、更に上腹に手を置き、臍下丹田に手を置いて
考えてみて、下元の力の有無、胸腹の支結壅塞等を打診し、果して合格点ありや否やを試みるべきである。
自ら思い半ばに過ぐるものがある筈である。
更に、翁の説くところを紹介しよう。
「それ日月星辰の中天に繋がるも、地界の万物を載せて重しとせざるも、悉(ことごと)く皆、その樞軸の運転あるに
よってなり。
人も亦かくの如く、身体を運転すべき大気を、この中心の丹田より輸(はこ)びて上下左右平等にして周遍(まわり
あまねき)ときには、自ら天賦の機関に合うが故に、求めずして不可思議の妙用を具(そな)え、変化自在の徳を有つ
にも至るべし。
若し、然る時は、心に憂愁憤怒の悩みもなく、楽境に係りて楽に着せず、かかるを天地と其の徳を同くし、日月と其の
明を合するものというべきなり」
求めずして不可思議の妙用を具うるに至るのは、要するに、自(おのずか)ら天賦の機関に格合するが故である。
一切の人為を去って、天然自然の大道に没入するが故に、求めずして天然自然の妙用を発するに至るのである。
所謂(いわゆる)人我の相を無くして、天地の心と一体化するものである。
|