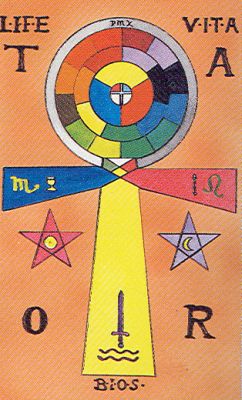
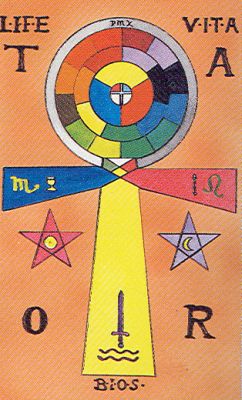
映画「アマデウス」
昨年度のアカデミー賞八部門をさらった、映画「アマデウス」が話題を集め、モーツアルトへの関心が高まっている。
この映画は、モーツアルトが宮廷音楽家として活躍したウィーン時代を中心に、彼の人生を描いたものだ。
物語は、当時、やはり音楽家として名声を博していた、サリエリと比較しながら展開されていく。
サリエリが、モーツアルトの才能を嫉妬していた事は、よく知られている。
彼は音楽家としての権威はあったが、才能の面では二流だった。
そして、モーツアルトの名声は、死後、大変な勢いで高まっていくのだが、その一方、サリエリの名は次第に忘れ去られていく。
そして、すっかり落ちぶれ、精神病院に入っている晩年のサリエリの追想の中で、モーツアルトの思い出がよみがえる
この映画に登場するモーツアルトは、一般的なモーツアルト像とはかなり違っていて、まったく捉え所がなく、遊び好き、女好きのひょうきんな男して
描かれている。
しかし、その男が作り出す音楽は、何と神々しい響きを放つことだろう。
音楽によって神に仕えようと考えていたサリエリは、神に問わずにいられない。
<神よ、あなたは音楽によって、あなたのメッセージを伝えるために、なぜあんな男を選んだのですか?>
彼は答えが得られないまま、神への信仰を捨ててしまう。
この映画を観て、サリエリに同情した人も多いと思う。
サリエリこそ、モーツアルトの才能を正しく評価し得た人物として描かれているからである。
しかしサリエリは、モーツアルトを最も理解していたようで、実は完全に理解するまでには至らなかった。
いつも嫉妬に燃えて、苦しみ続けていたのだ。
「アマデウス」で描かれているのは、モーツアルトのある一面でしかない。
それは、サリエリという人物の、嫉妬のメガネを通して見たモーツアルトなのだ。
我々がこの映画を基にして、モーツアルトの作品と、その人生の軌跡を辿るなら、更に多くのことを発見することができるだろう。
魂の音楽を求めて
私が音楽を意識して聴き始めたのは、中学生の頃である。
音楽は私を、内なる旅へと導いてくれた。
私は、その頃好んで聴いていたロックによって、大きな影響を受けた。
<私は異邦人である。宇宙人である。
いや、狂人であるかもしれない。
しかし、こんな狂った世界で平気な顔をしている人々こそ、狂っているのではないか!>
その頃、ロック音楽を聴きながら感じたのは、こんなメッセージであった。
それは、魂から発せられる叫びのように感じられた。
そして私は、その世界にのめり込んで行った。
だが当時の私は、なぜあんな重苦しいフィーリングの音楽に惹かれていったのだろう。
あの頃私達は、確かに何かを訴えてはいたが、心の奥底にある不満を感じても、解決策を見出す事は出来なかった。
その上、彼らの中には、アルコールや覚醒剤によって、廃人のようになった人も数多い。
そんな若者の一人であった私が、二年ほど前から、音楽に対する考え方を変え始めた。
私は、魂を揺さぶり、その奥深い所まで訴えかけてくる音楽を求めるようになっていた。
そして、モーツアルトとベートーベンに出会った。
クラシック音楽を聴くのは、初めは抵抗があったが、慣れてくると少しずつ、彼らの音楽と、私の魂が共振し合うのが感じられるようになった。
時には、静かな崇高な響きの中に、魂の安らぎを得て、愛と平和が実現するように心から願い、また、不安におののく時は激しい曲を聴いて、勇気と不屈の意思を
奮い立たせる。
私は、ピアノ曲、協奏曲、交響曲といった、親しみ易い作品から聴き始めた。
モーツアルトの作品では、ピアノ協奏曲第二十番、交響曲第三十八章「プラハ」、交響曲第四十番、そしてレクイエム等々、これらの作品は、映画「アマデウス」のバックにも流れていた、名曲の数々である。
オペラ「ドン・ジョバンニ」
「アマデウス」では、オペラの舞台も幾つか紹介されていた。
オペラは、ヨーロッパの伝統が生んだ芸術の中でも、最も華やかなものの一つであり、その中には、大変奥深いメッセージを伝えているものがある。
カバラや錬金術、また象徴学などの秘密の教えである。
大衆が鑑賞しても、それと気づかないように、それら秘密の叡智が、オペラの細部に散りばめられた。
モーツアルトのオペラ「ドン・ジョバンニ」も、よく知られた「魔笛」同様、そんな作品の一つである。
このオペラの主人公、ドン・ジョバンニは、冷酷な性の誘惑者である。
始めに彼は、ドンナ・アンナを犯そうと、彼女の部屋に忍び込む。
そこにアンナの父の騎士長がやって来て、娘を救おうとするが、反対にドン・ジョバンニに殺されてしまう。
こうして父を殺されたアンナは、ドン・ジョバンニへの復讐を誓うのだ。
このように、物語は、性と死の絡んだ事件から始まる。
それは、多くの神話や伝説とも共通している。
なぜならこの二つの問題は、我々の意識の最も奥深い所に、根ざしたものだからである。
私はこのオペラを、一人の人物に起こった内的な物語として捉えている。
だからここでは、私自身の内的な体験と、「ドン・ジョバンニ」のストーリーを重ね合わせて、見ていきたいと思う。
最初に、ドンナ・アンナについて語ろう。
ドンナ・アンナはある日、それまで体験した事のない、何か暗い衝動が内面から湧き上がり、それが心に襲い掛かるのを感じる。
この正体不明の黒い衝動こそが、ドン・ジョバンニという人物で象徴されているものだ。
ドン・ジョバンニは顔を隠し、長いマントに身を包んで登場する。
ドン・ジョバンニの魔手を逃れたアンナは、この犯人の正体を暴こうと、彼の後を追いかける。
これは、自分の内面を脅かす、悪魔的衝動が一体何なのかを知ろうとして、必死でもがいている状態だ。
そこにやって来るのは、アンナの父の騎士長である。
父は魂を象徴する。
それは、悪魔的衝動の反対の極であり、光を求め続ける、我々の本質である。
だから騎士長は、剣と灯りを持っている。
剣は意思の力を、灯りは叡智の光を象徴する。
こうしてアンナは、その内面に、気高い光と力が存在している事に気づくのである。
さて私も、思春期において、抑え難い性の衝動が湧き上がるのを体験した。
そしてそれは、強い期待と不安を孕んでいた。
特に恋愛事件や性的犯罪について雑誌で読んだりすると、大変興奮したものだ。
それらの事件は、とても他人事のようには思えず、私もいつか似たような問題に関わってしまうのではないか、と思い悩み、私の心を強く脅かした。
その上、そんな考えを誰かに知られる事を思うと、不安はますます高まるのだった。
あの頃、性は未だ、私の理解を超えていた。
この衝動は何なのか、生命を誕生せしめる性とは、一体何なのだろう。
そして、私はなぜ生まれて来たのだろうか。
私は性の中に、人智を超えた何かがある事を感じ始めた。
それは神秘的であり、汚してはならない神聖なものを含んでいるのではないかという思いが頭をよぎる事もあったが、やはり性は、私の理解の
及ばないものであった。
二年程前、性と心理について学ぶ機会を得て、私は性とは何かをようやく理解し始めた。
そして本来、性とは百パーセント神聖なものである事を知った。
ところが、その神聖なものを冒涜する事を想像すると、私の内面は未だに、
言いようのない願望と、強い罪悪感で入り乱れるのである。
本当は、そんな想像をしなければいいのだが、私の内面に渦巻く暗い衝動の強さには、自分でも驚くばかりだ。
しかし、人は誰もが、心の奥底では純粋な愛を求めている、と私は思う。
私が愛について意識するきっかけとなったのは、性の衝動と、それに対する嫌悪感である。
そのように、何らかのきっかけで罪悪感や自己嫌悪に陥る時、かえって人は、その対極にある、神聖な光を認識しうるのではないだろうか。
恋愛における愛と性について
このオペラ「ドン・ジョバンニ」は、人間の内面世界を様々な角度から分析し、構築したスケールの大きい作品である。
そこには、多くのメッセージが込められているが、その中でも性と愛は、「死」と共に、重要なメッセージとなっている。
大変興味深い人、ドンナ・エルヴィラという女性のエピソードがある。
彼女はこのオペラの中で、大変重要な役割を演じている。
ドンナ・エルヴィラは、ドン・ジョバンニの「愛」という言葉を信じて彼に身を任せるのだが、わずか三日で捨てられてしまう。
哀しみに沈む彼女に、ドン・ジョバンニの召使いのレポレロは、自分の主人がどんな男であるかを言って聞かせる。
それが、レポレロの歌うアリア、「カタログの歌」である。
「奥様、これが恋人のカタログ………イタリアでは六四〇人、ドイツでは
二三一人、スペインでは一〇〇三人……冬には太った女、夏は
やせた女、美人もブスも、相手を選ばず……。」
ドン・ジョバンニは女性を口説き、自分の手中に落ちた女性を名簿につけて、人数を増やす事ばかり考えている。
そんな彼は、自分の行っている事に対して、全ての女性を愛するのだ、と言ってのける。
しかし、彼の言う愛とは、官能的欲望以外の何ものでもない、だから、彼に騙されて傷ついたエルヴィラは怒り、復讐を誓うのだ。
彼女が望んでいたのは、純粋な愛だったからだ。
私も元来、非常に恋しやすいたちなのだが、いつも誰かを好きになるたびに、悩み始めることになった。
その湧き上がる情熱が愛なのか、それとも官能的な欲望でしかないのか、自分でも判らなかったからだ。
そこである時期、割り切って、官能的な快楽を満たすことに徹した事がある。
しかし結局判ったことは、私が求めているのは、これではないということだ。
快楽は一時的なものでしかなく、私の魂の渇望を満たしてくれるものではなかった。
ベートーヴェンは、次のように言っている。
「魂の結びつきのない官能の楽しみは
ただ動物的であるにすぎぬ。
事が終わって、何の高貴な感情のあともない。
むしろあるのは、悔恨だけだ。」
(ベートーヴェンの音楽ノート/猿田悳訳より)
愛は、魂の清らかな結びつきである、とも言われる。
そのような男女の気高い愛については、オペラ「魔笛」で描かれているが、その話しは次の機会に譲って、エルヴィラの話しに戻ろう。
騙されて復讐を決意した彼女だが、まだ心のどこかでドン・ジョバンニに魅かれるのを感じている。
するとそこにドン・ジョバンニはやって来て、涙声で、「今は後悔している、本当に愛しているのだ。」と、今度は彼女の感情に訴える。
それが、彼女の中の恋の残り火をかき立て、またもやドン・ジョバンニの手中に落ちてしまう。
再び騙された事を知った彼女は、前よりも更に酷い、絶望のどん底へと突き落とされる。
しかしその時、彼女の内面で、一つの変革が起こる。
求める愛から、与える愛へと変わるのだ。
苦悩の中で、彼女は祈る。
救いようのない男、ドン・ジョバンニの魂の為に祈るのだ。
そして彼女は、騙され、傷つく中で、代償を求める事のない、純粋な愛に目覚めていく。
彼女はドン・ジョバンニの死後、尼僧院へ向かう。
それは、万物への無限の愛を象徴するのだろうか。
エルヴィラは、真実の愛に気がついた女性であるが、このような愛を求める心は、誰もが持っているに違いない。
しかしその一方で、我々の内面世界には、ドン・ジョバンニという、悪魔的な力も存在しているのだ。
愛は官能的な欲望ではない。
また、単なる憧れや感傷的な気分でもない。
エルヴィラは、その二つを排除した。
慈悲心によって、ドン・ジョバンニに悔い改めるよう、涙ながらに訴える。
「この虐げられた魂は、
あなたから御恵みを求めません。」
真実の愛とは、このような犠牲的な献身であり、決して代償を求めないものだ。
私もそのような愛にようやく気づき始め、そこへ少しでも近づきたいと考えている。
火による浄化
一つの時代の終わりには、極端な性的頽廃がつきものである。
古代ローマ帝国の栄光の時代が終わる前もそうであったし、現在見られる性的頽廃も、一つの時代の終わりを暗示しているのかもしれない。
かつて私(筆者)は、世紀末の退廃的なデカダンの生活に対して、とても強い憧れを抱いていた。
思い描いた事は実現する、というのは本当で、実際私にも、そんな生活が始まった……。
ドアを開けると、神秘的な音楽が流れてくる。
薄暗いコンクリートの密室に、赤いスポットライト、インド香の香りと、ろうそくの灯り……このライブハウス「発狂の夜」の大きなテーブルを囲んで、
芸術家崩れの仲間が集まり、生ぬるい水割りを飲みながら、小さなステージを見る。
そこでは、性をもてあそぶ饗宴が始まり、朝方まで繰り広げられるのだった。
しかし、そんな生活も長くは続かず、やがて物質的快楽にも、退屈と虚しさを感じ出す時がきた。
私は真実の価値を求め始めていたのだった。
そして私はノーシスに巡り合い、性と心理についての確かな知識を得る事ができた。
その中に、プラクティスとしての、一つの呼吸法があった。
好奇心旺盛の私はすぐに実行したのだが、そうすると、脳細胞が活性化するような、爽やかな感覚が、すぐにやって来たのである。
そして、その時から、私の内面では、精神と物質の戦いが始まった。
その呼吸法によって、素晴らしいパワーと、崇高なエネルギーを、私自身が持っている事に気づき、それは、今までの退廃的な状態から脱しようと
決心するきっかけとなった。
さて、オペラ「ドン・ジョバンニ」の中で、喪服姿のアンナが、次のように語る場面がある。
「死だけが、私の涙を終わらせることができるでしょう。」
ここで言う「死」とは、自殺のことではない。
過去の自分が死んで、自由な存在として生まれ変わる事、「内的な死」を意味している。
こうして私は、過去の生活に別れを告げたのだが、それは決して順調な歩みではなかった。
多くの誘惑の声が、私の内面から沸きあがってくるのである。
私は、潜在する「火の力」を活動させて、内面を浄化する呼吸法を毎日、休む事なく続けた。
それは、心理的な苦痛を伴うもので、悪夢にうなされる日々が続いたこともあった。
しかしもう一方で、それまで縛られていたものから、徐々に解放されていくような、軽い感じも覚えるようになった。
やがて苦しみは終わった。
その時、私の中の一人の性的誘惑者(ドン・ジョバンニ)が死んだのである。
そして、私はとても自由になった。
丁度同じ頃、「発狂の夜」は、火災に遭って、店を閉じた。
最後の審判
モーツアルトは、「ドン・ジョバンニ」を通して、我々が内的平和に至るまでのプロセスである、「神秘的な死」を伝えている。
では、物理的な肉体の死について、モーツアルトはどのように考えていたのだろうか。
それは、彼が父親宛の手紙で述べている、次のような言葉によって、知る事が出来る。
「死は、(厳密に捉えれば)僕らの生の最終目標なのですから……(中略)
僕は、死が我々を真の幸福への鍵である事を知る機会を与えてくれた事で、神に感謝しています。」(モーツアルトの手紙 吉田秀和編訳)
この言葉から窺えるように、彼は肉体の死後も、我々の本質である霊魂は生き続け、真実の世界へ帰っていくことを、知っていたと思う。
このような死生観は、このオペラの最後の審判の場面において、明確に示されている。
それは、悪人ドン・ジョバンニの霊的世界における裁きである。
まず、彼の手によって殺された騎士長が、霊的世界の法を司る審判官として、ドン・ジョバンニの所にやって来る。
そして、未だ生きている彼を、死の審判へと招くのだ。
招きに応じた彼は、悔い改めるように忠告されるが、最後の最後まで拒み続ける。
そこで騎士長は消え、入れ替わるように悪魔達が現れる。
そして彼を、犯した罪にふさわしい、地獄の業火の中へと、引きずり込んでいくのだ。
この場面は、映画「アマデウス」においても紹介されていたが、モーツアルトの作品としては、
異常なほどの緊迫感で満ちた音楽が、物語のクライマックスを形作っている。
この裁きの少し前には、「もう飛ぶまいぞ、この蝶々は」の旋律が演奏される。
蝶々は、我々の解放された霊を象徴するのだが、ドン・ジョバンニと結びつける事によって、
一層、彼の霊魂は、もう救われない事が暗示されている。
そして、裁きが行われるのは、晩餐の時である。
豪華な食事をしているドン・ジョバンニの前に現れた騎士長は、次のように言う。
「天上の食物をとる者は、
地上の食物をとる必要はない」
天上の食物とは、魂の糧である。
すなわち彼は、物質的欲望を満たす事のみに専念して、精神的なものを培う事には、
何一つ興味を抱く事もなかたのだ。
石のように頑なになった彼の心は、悔い改めよという最後の警告さえも、受け入れる事が
出来ない。
「ドン・ジョバンニ」は、ダンテの「神曲」を参考にしたとも言われている。
「神曲」で示された死後の世界を描いた画家は大変多く、ミケランジェロの「最後の審判」も、
その一つで、地獄に落ちた人々の叫びが伝わってくるような情景がある。
そして、ドン・ジョバンニの地獄落ちの場面の音楽は、「最後の審判」を音で表現したような、
恐ろしいほどの迫力をもって、我々の心に訴えかける。
この場面の音楽を聞く時、私は惰性に過ごしている生活を悔い、心から改めようと決意せずにはいられない。
それは私の、この世的な欲望を粉々に打ち砕き、ダンテが「神曲」で描いた世界を、身近に感じさせてくれるからだ。
少数の理解者
こうしてドン・ジョバンニが葬られると、平和がやって来る。
そして最後に、次のように歌われて、このオペラは幕を閉じる。
「これが悪事の果て!
罪深い者たちの死はいつも、
彼らの生命に、同じ報いを受けるのだ」
モーツアルトは、このオペラ「ドン・ジョバンニ」を、少数の友人と、自分の為に書いた、と言っている。
なぜなら、「性の神秘」は、その当時、一般には明かされない教えだったので、モーツアルトは象徴的な表現を用いなければならなかったからだ。
ふしだらな貴族、ドン・ジョバンニの伝説は、そのメッセージを伝えるには、格好の題材だったのだろう。
モーツアルトは、音楽によって、我々に真実を伝えたのだ。
その偉大な仕事の数々も、彼にとっては、きっと永遠なる世界へ向けての旅支度だったのかもしれない。